私はデータ分析を支援するコンサルタントとして、これまで多くの企業を支援してきました。
その中でも特に印象深いのが、製造業A社に転職した元部下の佐藤さん(仮名)の事例です。
彼は入社当初、どれだけ丁寧な分析をしても「よく分からない」「現場の感覚と違う」と言われ続け、孤立していました。
しかし1年半後、彼の周りには「データで見てほしい」と相談に来る人が絶えなくなったのです。
組織が一夜にして変わったわけではありません。
彼が実践したのは、地道で、しかし確実に人の心を動かす3つの仕掛けでした。
今日は、データドリブンへの抵抗が強い組織を、内側から変えていった彼の実践ストーリーをお伝えします。
あなたの職場でも、明日から応用できる具体的な方法が見つかるかもしれません。
Contents
- 絶望から始まった物語
- 5秒でスルーされた分析資料
- なぜ「データ嫌い」が生まれるのか
- 戦略の転換点
- 仕掛け1:「最初の味方」を戦略的に選ぶ
- トップではなく、現場のエースを狙う
- エースの見つけ方と観察のコツ
- ポイント1:会議の様子
- ポイント2:日常の雑談
- ポイント3:課題意識の有無
- 「教えてください」から始まる信頼構築
- 仕掛け2:「小さくて確実な勝ち」を一緒に作る
- 成功するテーマ選びの3つの条件
- 条件1:本当に困っている
- 条件2:すぐ結果が出る
- 条件3:実現の確信が持てる
- 山本さんの本当の悩み
- 相手を巻き込むプロセス設計
- 小さな勝利がもたらした変化
- 仕掛け3:成功を「横に広げる」仕組みを作る
- 本人の口から語ってもらう戦略
- 自然な横展開を生む空気作り
- 使いやすさを追求したツール設計
- 地道な個別サポートの積み重ね
- データドリブン組織を作る本質的な教訓
- データではなく、人を主役にする
- 信頼を築く5つの行動原則
- ① 謙虚さ
- ② 傾聴
- ③ 他責にしない
- ④ 手柄を譲る
- ⑤ 約束厳守
- 1年半後の組織の変化
- 誰にでもできる「最初の一歩」
- 特別な才能は必要ない
- 段階的なロードマップ
- 最初の1ヶ月
- 次の1ヶ月
- 3ヶ月目以降
- 孤独なときの支え
- 今回のまとめ
絶望から始まった物語
5秒でスルーされた分析資料
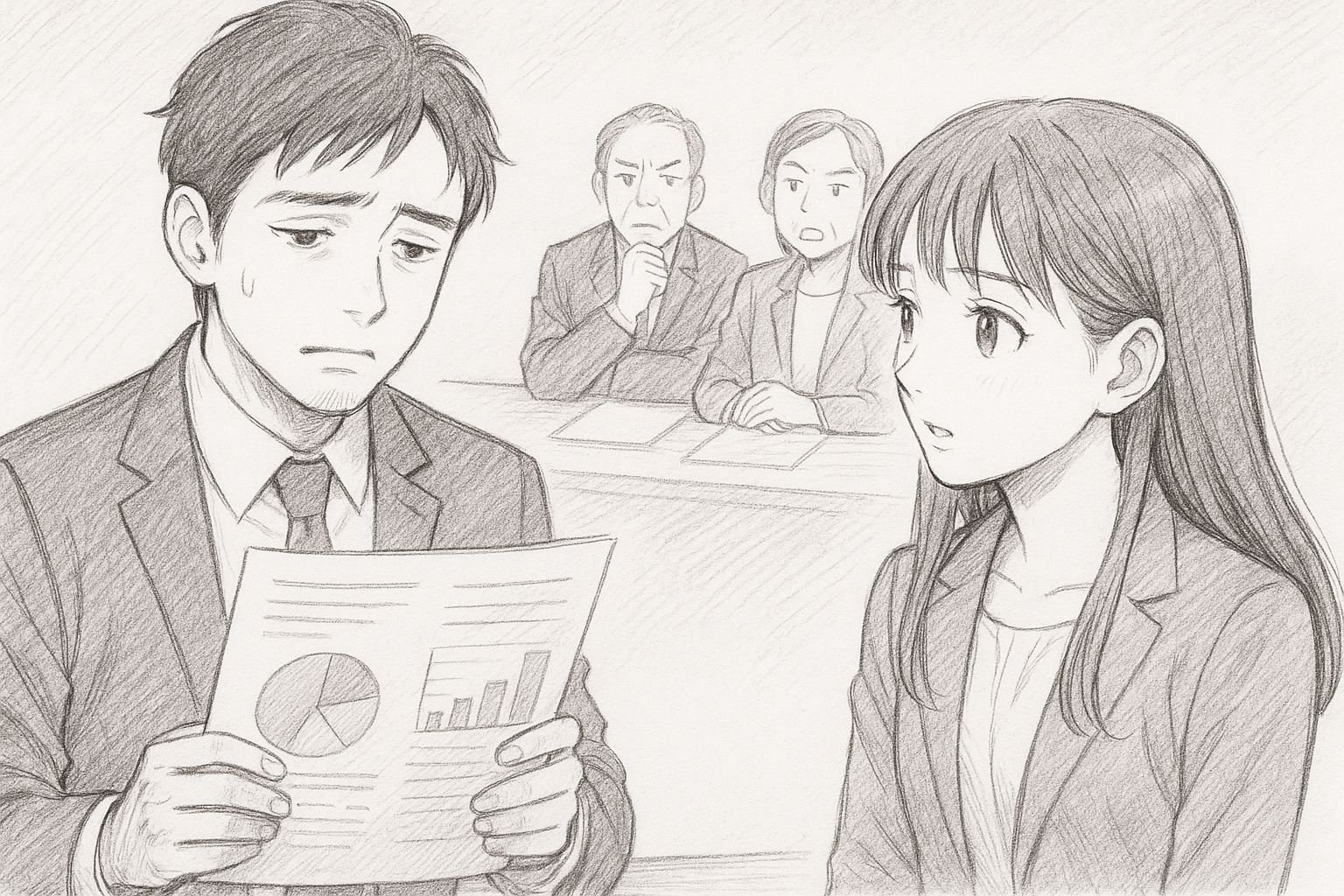
佐藤さんが初めて私に連絡をくれたのは、彼がA社に転職して半年が経った頃でした。電話口の声には、疲労と挫折感が滲んでいました。
「週末をかけて作った分析資料が、会議で5秒も見られずにスルーされたんです」
彼は製造業A社に、データサイエンティストとして中途入社しました。
前職ではIT系企業で働いており、データ分析によって関連企業の売上を12パーセント改善した実績もある、優秀な人材です。
しかし、この会社では全く状況が違っていました。
入社して最初に取り組んだのは、製造ラインの稼働データの分析でした。
数週間かけて丁寧にデータを整理し、効率化のポイントを特定し、きれいなグラフと共に提案資料を作成しました。
ところが、経営会議でその資料を提示したところ、製造部長の反応は冷淡なものでした。
「ああ、でもね、うちは現場のベテランの勘が一番正確だから」
その後ろで、現場のリーダー格である山本さん(仮名)が「データよりも実際の製品を見ないとね」と相槌を打ちました。
佐藤さんの提案は、それ以上議論されることもなく、次の議題に移ってしまったのです。
なぜ「データ嫌い」が生まれるのか

私が最初に佐藤さんにお伝えしたのは、組織がデータドリブンに抵抗を示す本当の理由についてでした。
多くのデータ分析者は「論理的思考ができない人たち」「数字が苦手な人たち」と相手を捉えてしまいます。
中には、データリテラシーが低いと現場やマネジメント層の方々を小馬鹿にする人までいます。
しかし、これは問題の本質を見誤っています。
本当の理由は、もっと人間的で、感情的なものなのです。
それは「信頼の欠如」という一言に集約されます。
考えてみてください。
製造現場で20年働いてきたベテランが、その間に培った経験で品質を守ってきたとします。
そこに、現場経験のない若手の分析者が現れて「データを見ると、あなたのやり方には改善の余地があります」と言ってきたら、どう感じるでしょうか。
おそらく、素直に受け入れることは難しいはずです。
A社にも、実は「データ分析の失敗体験」が潜んでいました。
佐藤さんが後から知ったのですが、5年前に経営企画本部の依頼を受けたコンサルタントが「データドリブン経営」を掲げ、現場の実態を無視した指標を押し付けてきた歴史があったのです。
その結果、現場は大混乱に陥り、かえって生産性が下がってしまいました。
この苦い記憶が、組織のDNAに刻まれていたのです。
山本さんたちは「データ」が嫌いなのではなく、「自分たちを理解しようとせずに、データを押し付けてくる人」に対する警戒心を持っていたのです。
戦略の転換点
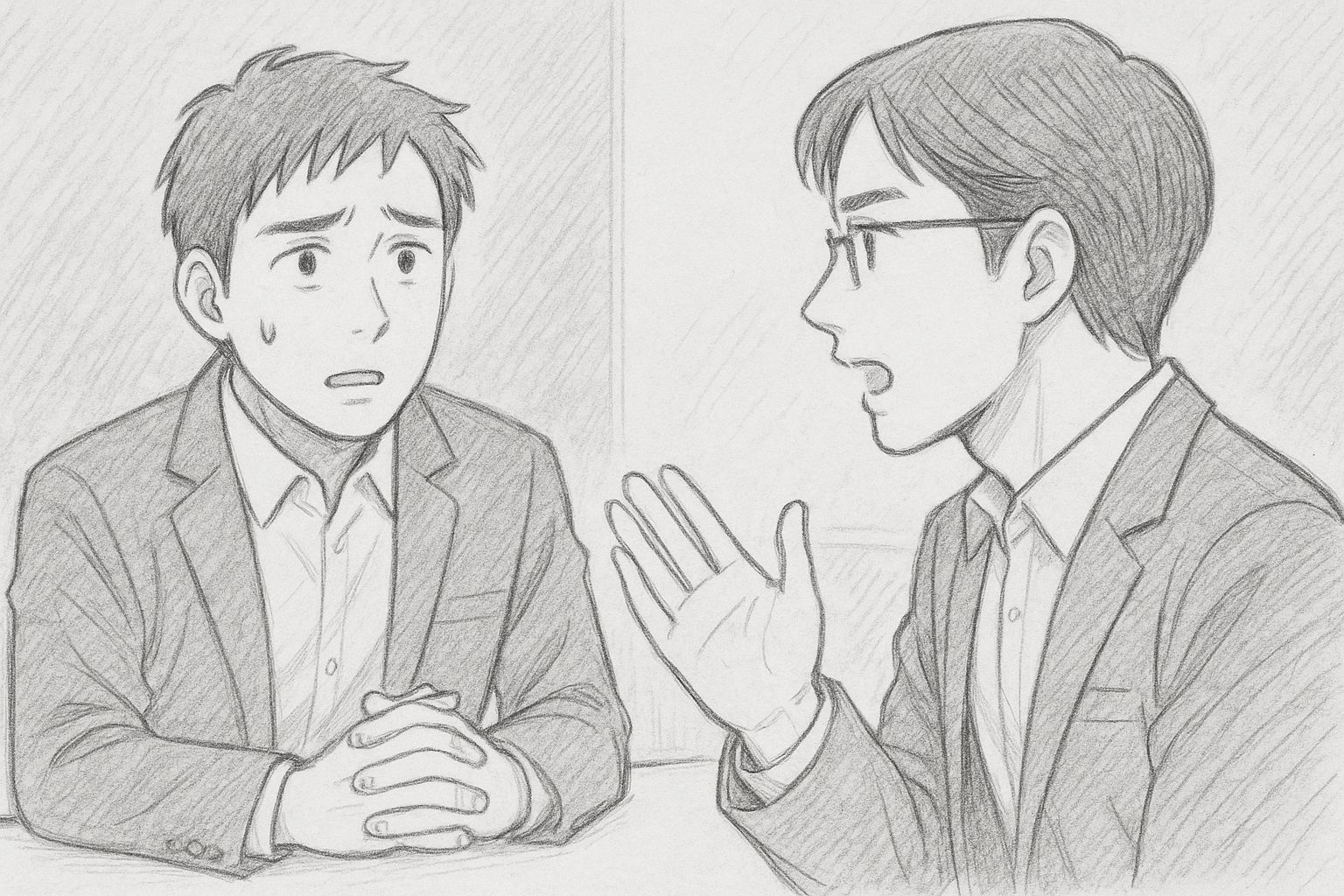
私は佐藤さんに、アプローチの根本的な転換を提案しました。
相手を変えようとするのではなく、まず自分が信頼される人間になること。データの正しさを証明するのではなく、相手の課題を本気で解決しようとする姿勢を示すこと。
この方向転換は、簡単ではありませんでした。
佐藤さんは前職での成功体験があり、「正しい分析をすれば、人は動くはず」という信念を持っていました。
その信念を一旦脇に置き、全く違うアプローチを試すことに、最初は抵抗もあったようです。
しかし、彼は決断しました。
「このままでは何も変わらない。やってみます」と。
この決断が、その後の展開を大きく変えることになりました。
仕掛け1:「最初の味方」を戦略的に選ぶ

トップではなく、現場のエースを狙う
組織を変えようとするとき、多くの人が経営層や上司を最初のターゲットにしてしまいます。
佐藤さんも当初、生産本部長を説得しようとしていました。
しかし私は、全く違うアプローチを提案しました。
「現場で最も影響力のある人を、最初の味方にしましょう」
それは組織図上の役職者ではなく、実際に現場を仕切り、周囲から信頼されているベテランリーダーです。
A社では、それが山本さんでした。
彼は役職としては係長でしたが、現場では30年のキャリアを持ち、若手からも経営層からも一目置かれる存在でした。
なぜ経営層ではなく、現場のエースなのか。理由は3つあります。
第一に、現場のエースが動けば、実際の業務がすぐに変わります。
経営層が方針を決めても、現場が動かなければ何も変わりません。しかし現場のエースが「これはいい」と言えば、周囲は自然と注目します。
第二に、彼ら・彼女らは具体的な課題を抱えています。
経営層の課題は抽象度が高く、データ分析の効果を実感してもらうまでに時間がかかります。一方、現場のエースは日々の業務で具体的な困りごとを持っており、それを解決できれば即座に価値を感じてもらえます。
第三に、成功すれば横展開がしやすいのです。
同じ現場で働く仲間が「山本さんがやってることなら、自分もやってみよう」と思う心理的ハードルは、「経営層が決めたことだから」という場合よりもはるかに低いのです。
エースの見つけ方と観察のコツ
では、どうやって「現場のエース」を特定するのか。
私は佐藤さんに、3つの観察ポイントを伝えました。
ポイント1:会議の様子
まず、会議や打ち合わせでの発言を注意深く観察することです。
ある人が何か言ったとき、周囲がどのような反応を示すか。真剣に耳を傾けているか、メモを取っているか、頷いているか。
他のメンバーが「○○さんはどう思いますか」と意見を求めるか。こうした場面が頻繁に見られる人が、影響力を持つ人です。
ポイント2:日常の雑談
次に、日常の雑談での情報収集です。
ランチや休憩時間に、他の社員と何気ない会話をする中で「製造現場で一番頼りになる人って誰ですか」「困ったとき、誰に相談しますか」といった質問を、さりげなく投げかけます。
複数の人から同じ名前が出てきたら、それが「現場のエース」です。
ポイント3:課題意識の有無
そして最も重要なのが、その人自身が課題意識を持っているかどうかです。
佐藤さんが山本さんに注目したのは、彼が影響力を持っていただけでなく、「若手の技術継承がうまくいかない」という悩みを持っていることを、偶然の立ち話で知ったからでした。
課題意識のある人は、解決策に対してオープンなのです。
「教えてください」から始まる信頼構築
エースを特定したら、次は関係構築です。
ここで佐藤さんが実践したのは、「データ分析者」としてではなく「学びたい人」として接することでした。
彼は思い切って、山本さんに声をかけました。
「現場のことを全く知らないので、教えていただけませんか。1日、作業を見学させてもらえないでしょうか」
最初、山本さんは面倒くさそうな表情をしました。
しかし佐藤さんの真剣な眼差しに、彼は「まあ、邪魔にならない程度ならいいよ」と承諾してくれました。
見学当日、佐藤さんは作業着を着て、朝7時から現場に入りました。
山本さんの動きを観察し、質問し、メモを取りました。機械の音、油の匂い、作業員の動き。データでは決して分からない、現場の機微を肌で感じる一日でした。
そして何より重要だったのは、見学後に佐藤さんがしたことです。
彼は翌日、手書きのメモを山本さんに渡しました。
そこには「昨日学んだこと」が丁寧にまとめられており、特に印象に残った山本さんの言葉が引用されていました。
「機械の微妙な音の変化で、不良品が出る前に分かるんですね。これは本当にすごい技術だと思いました」
このメモが、山本さんの心を動かしました。
自分の経験を真剣に学ぼうとする姿勢、具体的に何を学んだかを言語化する努力。
山本さんは後日、こう語ったそうです。
「あのメモを見て、この人は本気なんだと思った。それまでの分析者とは違うと感じたんだ」
人は、自分の経験を尊重し、真剣に学ぼうとする人に対して、心を開くものです。
この「教えてください」というスタンスこそが、信頼関係の第一歩になるのです。
仕掛け2:「小さくて確実な勝ち」を一緒に作る

成功するテーマ選びの3つの条件
信頼関係ができたら、次は「最初の成功体験」を作るフェーズです。
ここでのテーマ選びが、その後の展開を大きく左右します。
私は佐藤さんに、最初のプロジェクトには厳しい条件をつけることを提案しました。
条件1:本当に困っている
第一の条件は、相手が本当に困っている課題であることです。
建前ではなく、本音の困りごと。
毎日の業務で実際に頭を悩ませている問題でなければなりません。
多くの場合、文章化も言語化もされていません。
条件2:すぐ結果が出る
第二の条件は、1週間から2週間で結果が見えることです。
長期プロジェクトは避けるべきです。
なぜなら、最初の挑戦では「データ分析は役に立つ」という体験を、できるだけ早く実感してもらう必要があるからです。
条件3:実現の確信が持てる
第三の条件は、あなたが絶対に解決できると確信が持てることです。
最初の挑戦で失敗すると、せっかく築いた信頼を失い、取り戻すのは非常に困難になります。
成功確率が高いテーマを選ぶことが重要なのです。
山本さんの本当の悩み
佐藤さんは、山本さんとの雑談の中で、あることに気づきました。
彼が頻繁に口にする言葉がありました。「若い子に教えても、なかなか身につかないんだよな」
ある日、佐藤さんは思い切って聞いてみました。
「山本さん、若手の育成で一番困っていることって何ですか」
山本さんは少し考えてから、こう答えました。
「不良品の予兆を見分ける感覚かな。俺は音や振動で分かるんだけど、それを言葉で教えるのが難しくてさ。結局、何年も経験を積まないと分からないってことになっちゃう。でも、それじゃあ人が育つのに時間がかかりすぎるんだ」
これだ、と佐藤さんは思いました。
この課題なら、データで何かできるかもしれない。
山本さんの「暗黙知」をデータで可視化し、若手でも分かる形にできれば、技術継承の助けになるはずです。
相手を巻き込むプロセス設計
佐藤さんは提案しました。
「山本さんの感覚を、データで見える化できないか試してみたいんです。機械のセンサーデータと、不良品が出たタイミングを照らし合わせれば、何かパターンが見つかるかもしれません」
ここで彼が使った言葉に注目してください。
「できます」ではなく「試してみたい」と言ったのです。
これなら、仮に失敗しても「まあ、試しただけだし」と受け止めてもらえます。
成功を約束せず、一緒に挑戦する仲間としての立ち位置を示したのです。
山本さんは興味を示してくれました。
「本当にそんなことできるのか。まあ、やってみる分にはいいけど」
分析を進める際、佐藤さんは意識的に山本さんを巻き込みました。
データを見ながら「この振動の変化、現場的にはどう感じますか」「このタイミングで何か特別な作業をしていますか」と、頻繁に確認を取りました。
これには2つの意味がありました。
一つは、データと現場の感覚を擦り合わせることで、分析の精度を高めること。データだけを見ていても分からない、現場ならではの文脈があります。
もう一つは、山本さんに「積極的に関わっている」という当事者意識を持ってもらうことです。
人は、自分が関わったプロジェクトには愛着を持ちます。
「佐藤さんが作ったツール」ではなく「自分たちで作ったツール」という認識を持ってもらうことが、後の展開で重要になってきます。
小さな勝利がもたらした変化
1週間後、佐藤さんは結果を持って山本さんのもとを訪れました。
センサーデータの分析から、不良品が発生する24時間前に、特定の振動パターンが現れることを発見したのです。
さらに彼は、その振動パターンを自動検知して、担当者にアラートを出すシンプルなシステムも試作していました。
複雑なダッシュボードではなく、赤いランプが点灯するだけの、誰でも分かる仕組みです。
山本さんは最初、半信半疑でした。
「これで本当に分かるのか」。
しかし、1週間試験運用したところ、アラートが出た翌日に実際に不良品が発生したケースが3回ありました。
逆に、アラートが出なかった日は、不良品がほとんど出ませんでした。
2週間後、山本さんは佐藤さんにこう言いました。
「すごいな、これ。俺が20年かけて身につけた感覚を、データで再現できるなんて思わなかった。若手もこれがあれば、もっと早く一人前になれるかもしれない」
彼の目は輝いていました。そして、その変化は言葉だけではありませんでした。
山本さんは製造部の定例会議で、自らこのシステムのことを話し始めたのです。
「佐藤さんと一緒に作ったんだけどさ」と、誇らしげに。
これが、佐藤さんと山本さんの「最初の小さな勝ち」でした。
不良品発生率が12パーセント減少したという数字も重要でしたが、それ以上に価値があったのは、山本さんの認識が変わったことでした。
「データって、こういう使い方するのか」と、彼は初めて「データの価値」を体感したのです。
仕掛け3:成功を「横に広げる」仕組みを作る

本人の口から語ってもらう戦略
一人のエースを味方につけただけでは、組織は変わりません。
ここからが、最も繊細で、かつ重要なフェーズです。
多くの分析者がここで失敗するのは、自分から「山本さんでうまくいったので、みなさんもどうですか」と売り込んでしまうことです。
これでは、また「押し付け」になってしまいます。
せっかく作った成功事例が、「分析チームの宣伝」として受け取られ、現場の共感を得られません。
私が佐藤さんに提案したのは、山本さん自身に語ってもらう戦略でした。
成功した本人が、自分の言葉で、その価値を伝える。
これが最も説得力を持つのです。
ちょうど月例の製造部会議があったので、佐藤さんは事前に製造部長に相談しました。
「山本さんの不良品予知システム、他のラインでも興味があるかもしれません。会議で共有の時間をいただけませんか」
部長は了承し、会議の議題に「山本係長からの好事例共有」という項目を加えてくれました。
実は佐藤さんは、山本さんにも事前にお願いしていました。
「他のラインの人たちにも、きっと参考になると思うんです。山本さんから話していただけませんか」
自然な横展開を生む空気作り
会議当日、製造部長が「山本さん、最近不良率が下がってるね。何かコツでもあるの?」と水を向けました(実は、佐藤さんが事前に部長にも根回ししておいたのですが、その場では自然な流れに見えるよう配慮されていました)。
山本さんは少し照れながらも、こう語りました。
「実は、データ分析チームの佐藤さんと一緒に、不良品の予兆を検知するシステムを作ってさ。俺の感覚をデータで見える化してくれたんだよ。これが意外と当たるんだ。若手も使いやすいって言ってくれてる」
この「本人の口から語られる成功体験」が、何よりも説得力を持ちます。
佐藤さんが100回説明するよりも、山本さんの一言の方が、現場の心を動かしたのです。
会議後、何人かの現場の方が佐藤さんのところに来ました。
「山本さんが使ってたやつ、うちのラインでも試せる?」「センサーデータの見方、教えてもらえないかな」
佐藤さんは、個別対応するのではなく、もう一歩踏み込みました。
山本さんと作った分析を「テンプレート化」したのです。
使いやすさを追求したツール設計
他のラインでも使える「不良予兆チェックシステム」を作り、簡単な使い方マニュアルと一緒に共有フォルダに置きました。
重要なのは、これが専門的な分析ツールではなく、誰でも使えるシンプルなものだったことです。
システムは、センサーデータを自動で読み込み、異常パターンを検知したら、担当者のスマートフォンに通知が来る仕組みでした。
難しい設定は不要です。初回に自分のラインの機械番号を登録するだけで、後は自動で動きます。
そして佐藤さんは、このシステムに「山本システム」という愛称をつけました。
「データ分析チームが作ったもの」ではなく、「山本さんが最初に使って成果を出したシステム」として位置づけたのです。
こうすることで、現場の方たちは「新しいデータツール」に対してではなく、「先輩である山本さんのやり方」に対して心を開いてくれました。
「山本さんがやってることなら、俺もやってみようかな」という心理が働いたのです。
地道な個別サポートの積み重ね
最初の1ヶ月で、5つのラインがシステムを導入しました。
しかし、全てがスムーズにいったわけではありません。
あるラインでは、機械の種類が違ったため、山本さんのラインで見つけたパターンが当てはまりませんでした。
佐藤さんは、そのラインの現場リーダーと一緒に、そのライン専用のパターンを分析しました。
数日かけてデータを見直し、その機械特有の予兆パターンを発見しました。
この「一人ひとりに向き合う姿勢」が、さらなる信頼を生んだのです。
3ヶ月後には、製造部門の8割のラインが何らかの形でシステムを使うようになっていました。
そして半年後、製造部長が部会議でこう宣言しました。
「不良予兆システムは、全ラインで標準装備にします。新人教育のカリキュラムにも組み込みましょう」
佐藤さんは何も強制していません。
山本さんの成功が、自然と周囲に伝播していったのです。
焦らず、1人から3人、3人から10人へ。ゆっくりと、しかし確実に広がっていきました。
データドリブン組織を作る本質的な教訓
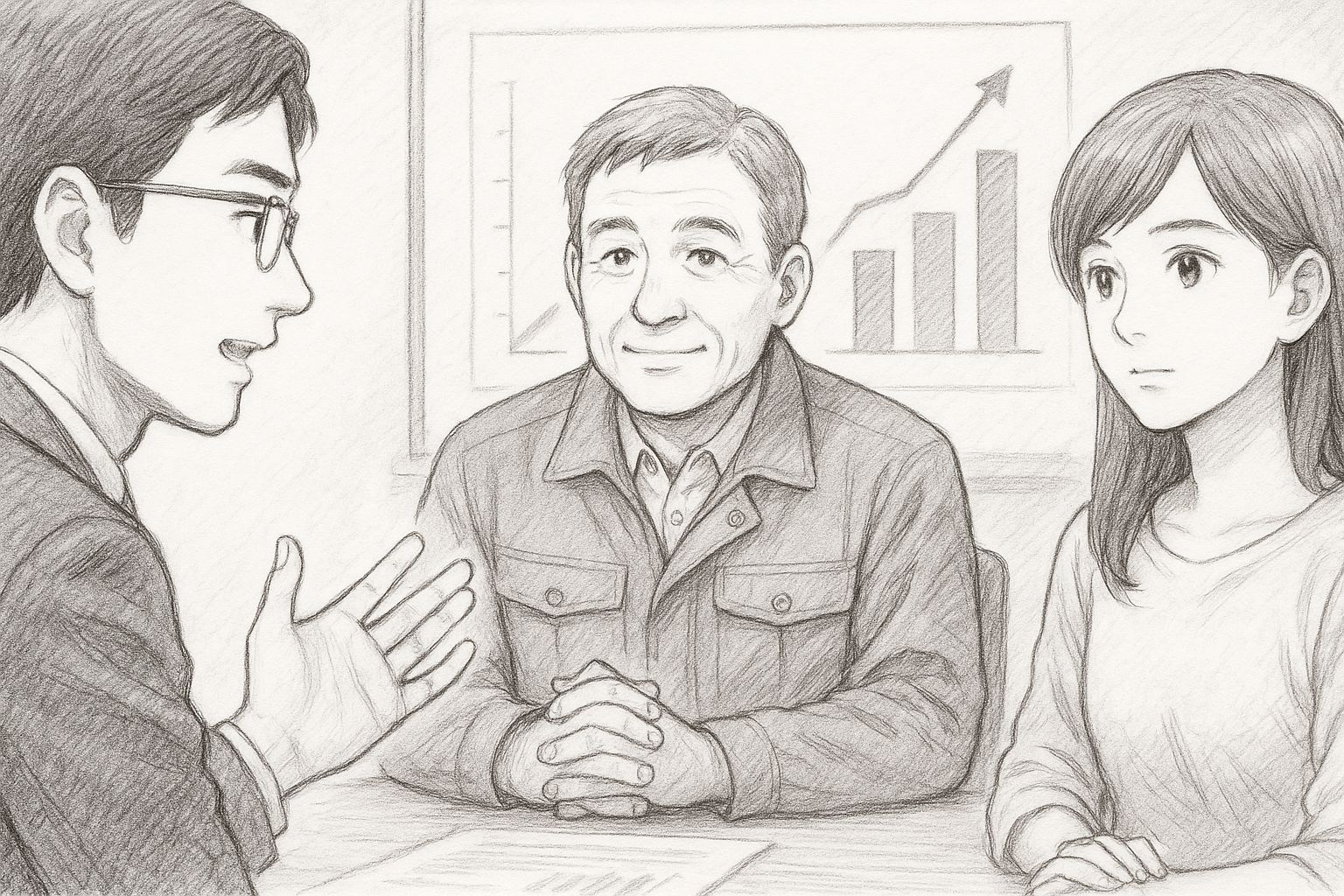
データではなく、人を主役にする
ここまで、佐藤さんが実践した3つの仕掛けを見てきました。
現場のエースを味方につけ、小さな成功を一緒に作り、それを横に広げていく。この一連のプロセスで、私が彼に最も強調したことがあります。
それは「データを主役にしない」ということです。
矛盾しているように聞こえるかもしれません。
データドリブンな組織を作りたいのに、データを主役にしない。これこそが核心なのです。
人は「データ」を信頼するのではありません。
人は「人」を信頼するのです。
あなたが信頼されれば、あなたが提示するデータも信頼される。
あなたが現場の課題を本気で解決しようとしていることが伝われば、データは単なる数字から「役立つ道具」に変わるのです。
佐藤さんは当初、正しい分析結果を示せば、人は動くと思っていました。
前職での成功体験が、その信念を強化していました。
しかし実際には、分析の精度よりも、分析者の姿勢の方が、はるかに重要だったのです。
信頼を築く5つの行動原則
佐藤さんの事例から、私たちは信頼を築くための具体的な行動原則を学ぶことができます。
① 謙虚さ
第一に、「教えてください」と現場に頭を下げる謙虚さです。
自分の専門性を誇示するのではなく、相手の専門性を尊重する姿勢が、対話の扉を開きます。
② 傾聴
第二に、相手の言葉に真剣に耳を傾ける誠実さです。
表面的に聞くのではなく、その言葉の背後にある感情や文脈まで理解しようとする努力が、相手に伝わります。
③ 他責にしない
第三に、失敗したときに言い訳せず、一緒に解決策を探す責任感です。
うまくいかなかったとき、データや手法のせいにするのではなく、「では、どうすればいいか一緒に考えましょう」という姿勢が信頼を深めます。
④ 手柄を譲る
第四に、成果を自分の手柄にせず、相手を立てる懐の深さです。
「私が分析しました」ではなく「山本さんと一緒に作りました」と言うことで、相手に当事者意識が生まれます。
⑤ 約束厳守
第五に、小さな約束を確実に守る誠実さです。
「来週までに結果を出します」と言ったら、必ず守る。この積み重ねが、信頼の基盤になります。
こうした人間的な信頼の上にしか、データ文化は根付きません。技術や手法よりも、まず人として信頼されることが、全ての始まりなのです。
1年半後の組織の変化
佐藤さんの取り組みから1年半が経った今、A社には確実に変化が起きています。
山本さんは今、新入社員の教育係をしていて、「製造はまずデータを見てから動け」と指導しています。
「俺も最初はデータなんて信じてなかったけどさ」と笑いながら。
製造部だけでなく、営業部門や品質管理部門からも「データで見てみたい」という相談が増えました。
佐藤さんのもとには、週に10件以上の相談が寄せられるようになりました。
そして最も象徴的だったのは、先日の全社会議での社長の発言でした。
「うちの製造部が変わってきたね。現場発でデータ活用が広がっているのは素晴らしいことだ。他の部門も見習ってほしい」
トップダウンではなく、ボトムアップで変化が起きた。これこそが、持続可能な組織変革の姿なのです。
強制された変化は、推進者がいなくなれば元に戻ります。
しかし、現場から生まれた変化は、組織の文化として定着していきます。
誰にでもできる「最初の一歩」
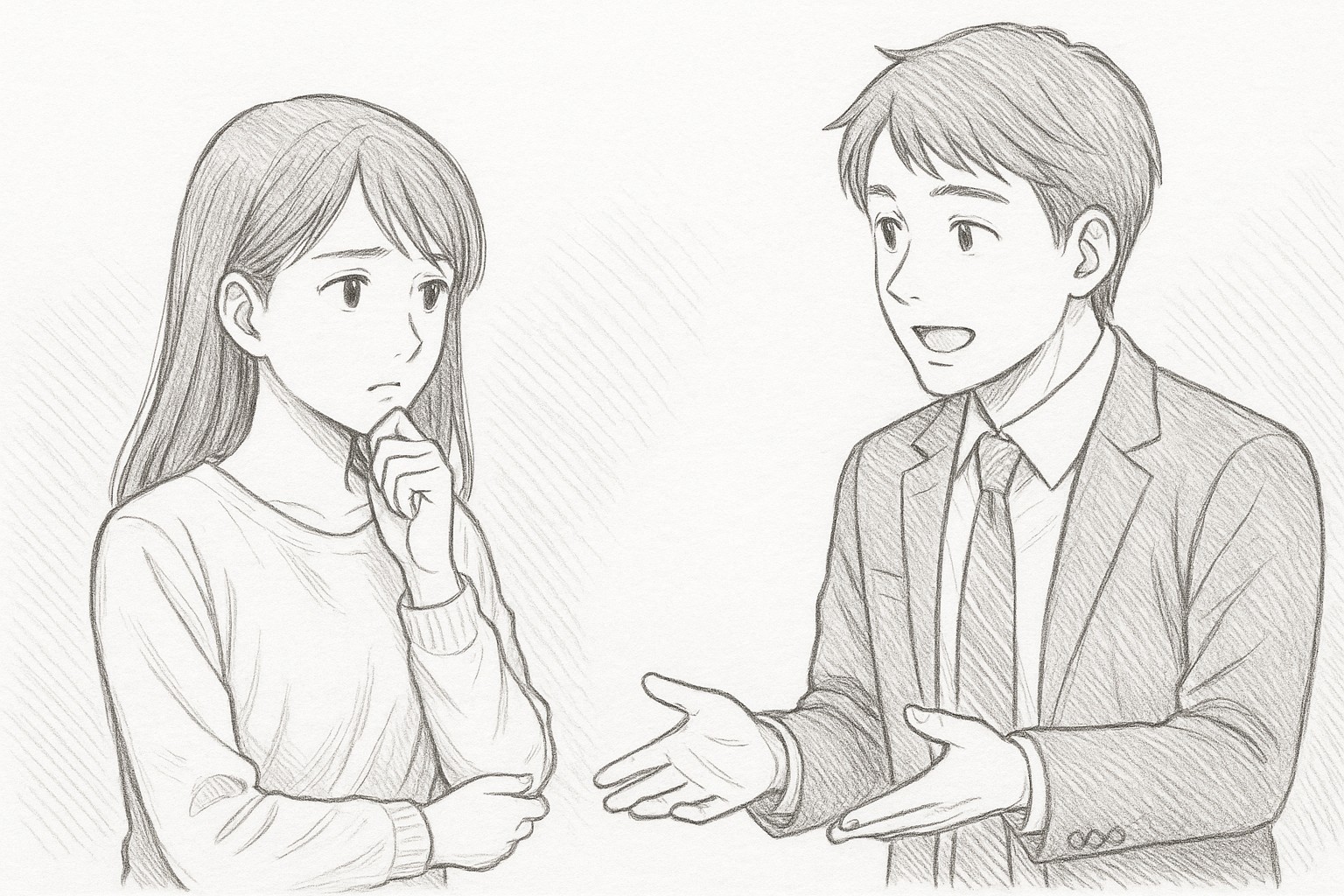
特別な才能は必要ない
この事例を読んで、「自分にもできるだろうか」と不安に思う人もいるかもしれません。
組織を変えるなんて、大それたことに聞こえるかもしれません。
しかし、佐藤さんも最初は、孤独で、無力感を感じていました。
彼が特別だったのは、能力や才能ではありません。
ただ一つ、「諦めずに、アプローチを変えてみる、小さな勇気」を持っていたことです。
必要なのも、特別な才能でも、カリスマ性でもありません。
必要なのは、明日、誰か一人に「何か困っていることありますか」と声をかける勇気だけです。
その一言から、すべてが始まります。
相手の話を真剣に聞く。現場を学ぶ。小さな課題を一緒に解決する。
その積み重ねが、半年後、1年後の組織を変えていくのです。
段階的なロードマップ
具体的に、どのように進めればいいのか。
佐藤さんの事例から、実践的なロードマップを整理しましょう。
最初の1ヶ月
最初の1ヶ月は、観察と関係構築の期間です。
現場に足を運び、人々の会話を聞き、誰が影響力を持っているかを見極めます。
そして、その人との信頼関係を築くことに集中します。
次の1ヶ月
次の1ヶ月は、課題の特定と小さなプロジェクトの実行です。
相手が本当に困っていることを聞き出し、確実に解決できる小さなテーマを選びます。
そして、相手を巻き込みながら、一緒に成果を作ります。
3ヶ月目以降
3ヶ月目以降は、横展開のフェーズです。
成功事例を本人に語ってもらい、ツールをテンプレート化し、個別サポートを丁寧に行いながら、少しずつ広げていきます。
焦る必要はありません。組織の変化には時間がかかります。
しかし、確実に一歩ずつ進んでいけば、必ず変化は起きます。
孤独なときの支え
データ分析者の戦いは、時に孤独です。
理解されない悔しさ、努力が報われない虚しさ。そんな感情に押しつぶされそうになることもあるでしょう。
佐藤さんも、何度も心が折れそうになりました。
そんなとき、彼を支えたのは、社外のデータ分析コミュニティでした。
同じような悩みを持つ仲間と話すことで、「自分だけじゃないんだ」と思えたそうです。
もしあなたが今、孤軍奮闘しているなら、同じ戦いをしている仲間を探してください。
勉強会やオンラインコミュニティに参加してみてください。あなたは決して一人じゃありません。
今回のまとめ
データドリブンに抵抗を示す組織を変えるには、データの正しさを証明するのではなく、人としての信頼を築くことから始める必要があります。
現場で最も影響力のある人を最初の味方にし、その人が本当に困っている小さな課題を一緒に解決することで、最初の成功体験を作ります。
そして、その成功を本人の口から語ってもらい、使いやすいツールとして横展開することで、自然な形で組織全体に広げていくことができます。
組織の文化は一人では変えられません。
しかし、最初の火を灯す人には、誰でもなれます。
そして、その火は必ず周囲に広がっていきます。
明日、あなたの職場で、誰か一人に「何か困っていることありますか」と声をかけてみてください。
その一言が、1年後の組織を変える第一歩になるはずです。
データ分析者の本当の仕事は、正しい分析をすることではなく、データを通じて人と人をつなぎ、組織を少しだけ前に進めることなのです。

