需要予測の現場には、ちょっと不思議な光景があります。
「あの人の読みは大体当たる」と社内で評判のベテラン担当者がいます。
営業歴20年、取引先の空気を読む力には定評がある。
にもかかわらず、期末になると倉庫には売れ残った在庫が積み上がり、値引き処分や廃棄ロスが毎年のように発生します。
「当たっている」はずなのに、結果が合わない。
この矛盾の正体を理解しないまま、「もっと精度の高い予測を」と号令をかけても、同じことが繰り返されます。
問題は予測の「精度」ではなく、人間が予測するときに構造的に入り込むバイアス(偏り)の方向性にあるのです。
Contents
人間の予測は、構造的に「上に振れる」ようにできている

需要予測が上振れしやすい原因は、個人の能力不足ではありません。
人間の認知の仕組みそのものが、予測を上方向にずらす構造を持っています。
ここでは、実務でとくに影響が大きい3つのメカニズムを見ていきます。
① 楽観バイアス ―「うまくいくシナリオ」を重く見すぎる
人間は将来の見通しを立てるとき、成功するシナリオを実際よりも高い確率で起こると感じてしまう傾向があります。
これを「楽観バイアス」と呼びます。
需要予測の場面では、「あの大口案件が決まれば」「新商品のキャンペーンが当たれば」といった「条件付きの上振れシナリオ」として表れます。
ここで少し考えてみてください。
5つの好条件がそれぞれ50%の確率で実現するとして、そのすべてが揃う確率はどのくらいでしょうか。
答えは約3%です。
ところが、人間の頭の中では、それぞれの好材料がバラバラのポジティブ情報として積み上がり、「今期はいけそうだ」という感覚が形成されてしまいます。
冷静に確率を計算すれば3%にすぎないシナリオを、あたかも高い確率で起こるように感じてしまうわけです。
② アンカリング ―直近の「良かった時期」に引っ張られる
もうひとつ厄介なのが、「アンカリング効果」と呼ばれる現象です。
直近に売上が好調だった月や、大型受注があった四半期の記憶が、頭の中で「基準点」として固定されてしまい、その数字からの微調整で予測を組み立ててしまうのです。
ここで実務上見落とされがちなポイントがあります。
好調だった時期には、「たまたまうまくいった要因」が含まれていることが多いということです。
競合の欠品、天候、為替の変動、取引先の在庫調整サイクルなど、次も同じように再現される保証のない要因が売上を押し上げていた場合でも、人間はその数字を「自分たちの実力値」として記憶しやすいのです。
結果として、好調期をベースにした予測は、平均的な実力値よりも高い水準に偏ります。
③ 組織のインセンティブ ―「少なめに言う」ことの社内リスク
認知バイアスに加えて、組織内の力学も上振れを後押しします。
想像してみてください。
営業担当者が「来期の売上は前年比マイナスになりそうです」と報告する場面を。上司からは「やる気がないのか」と受け取られかねませんし、目標交渉の材料にもなりにくいでしょう。
一方で、「前年比110%を狙います」と言っておけば、たとえ未達に終わっても「チャレンジした結果」として処理される余地があります。
つまり、低く見積もることの社内コストが、高く見積もることの社内コストよりも大きいのです。
この非対称なインセンティブ構造がある限り、現場から上がってくる予測は構造的に上に偏ります。これは個人の誠実さの問題ではなく、組織のインセンティブ設計の問題です。
教科書が教えてくれない「上振れの本当のコスト」

需要予測が上に振れること自体は、「ちょっと多めに見積もった」という程度の話に聞こえるかもしれません。
しかし、上振れ予測を前提に組織が動いたとき、そのコストはさまざまなところに波及していきます。
ここが、教科書的な予測精度の議論では見えにくい部分です。
過剰在庫の直接的なコストだけでも、保管費用、資金が眠ることで生まれる機会損失、値引き処分による利益率の低下があります。
しかし、実務上もっと深刻なのは、判断の基準そのものが歪んでいくことです。
たとえば、上振れ予測に基づいて確保した生産枠や仕入れ枠が余ると、「せっかく確保したのだから使い切ろう」という力学が働きます。
本来なら不要だった販促施策が打たれ、値引きで在庫を掃くことになります。
すると、その値引き実績が翌期の「当たり前の水準」に組み込まれ、「値引きしないと売れない」という前提が固定化してしまいます。
上振れ予測が、自社の価格設定を内側から壊していくわけです。
さらに見落とされがちなのが、上振れ予測は「振り返り」を阻害するという問題です。
予測が上に外れた場合(予測より実績が低かった場合)、「市場環境が想定より悪かった」「競合が価格を下げた」などの外部要因で説明がつきやすく、予測プロセスそのものが検証されないまま翌期も同じ方法が繰り返されます。
逆に、予測が下に外れた場合(予測より実績が高かった場合)は「なぜ読み切れなかったのか」と原因究明が求められるのとは対照的です。
この非対称性に気づいているかどうかが、需要予測を改善できる組織とできない組織の分かれ目になります。
「人間が予測する」こと自体が悪いわけではない
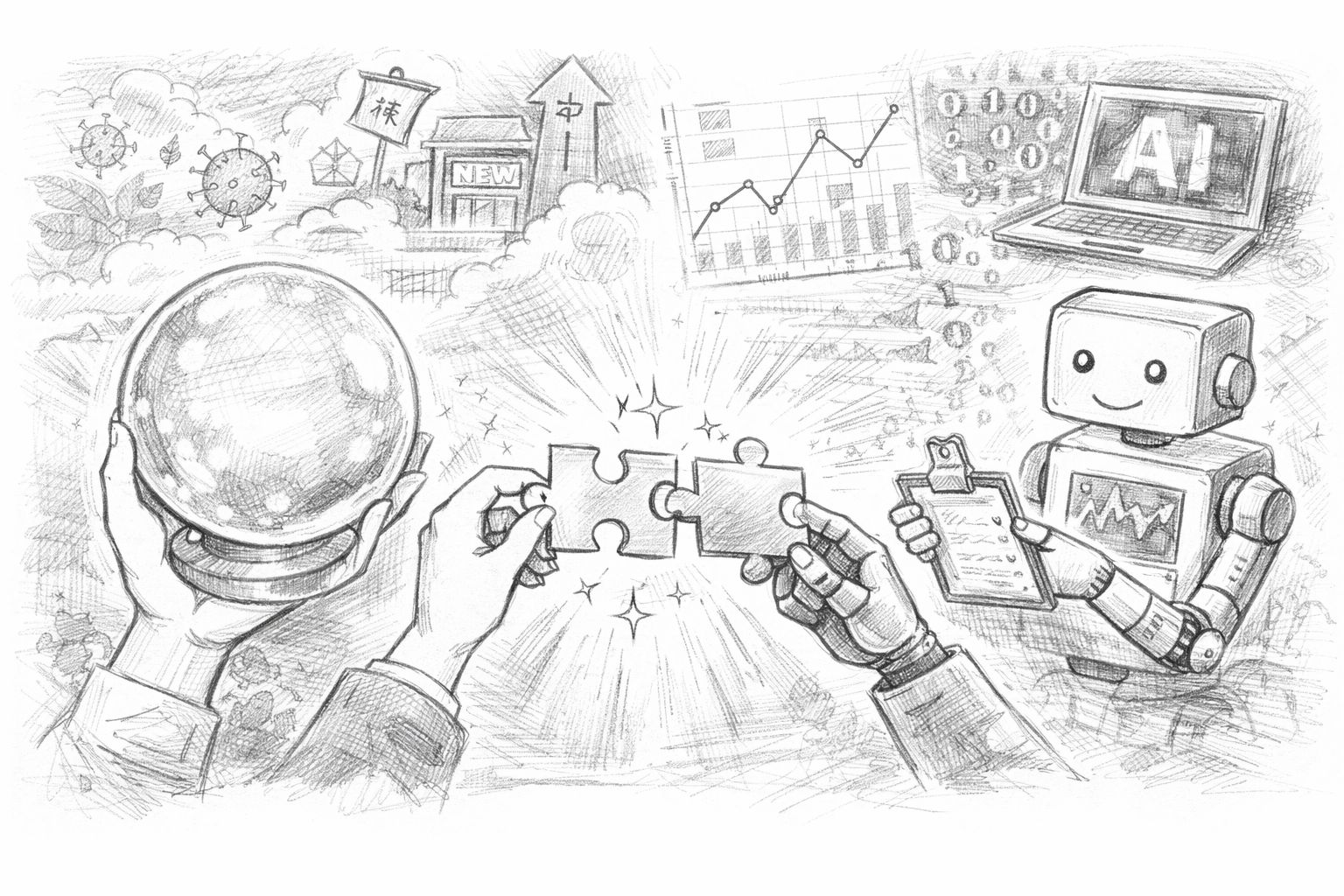
ここまで読むと、「だから人間の予測はダメで、統計モデルやAIに任せるべきだ」と結論づけたくなるかもしれません。
しかし、話はそう単純ではありません。統計モデルにも当然限界があります。
過去にないイベント(新しい競合の参入、法改正、パンデミックなど)はデータから予測できませんし、取引先との関係性の変化のように数字にしにくい情報は、現場の人間にしか感知できません。
大切なのは、人間の予測を排除することではなく、人間の予測に構造的に入り込むバイアスの方向と大きさを知ったうえで、それを補正する仕組みを持つことです。
実務で有効なアプローチをいくつかご紹介します。
ベースラインとの乖離を「見える化」する
たとえば、統計的な手法で算出したシンプルな予測値を「ベースライン(基準値)」として持っておき、現場の予測値との差分を常に見えるようにします。
「現場予測がベースラインより15%高い」という事実が可視化されるだけで、「この15%の根拠は何か」という問いが自然と生まれます。この問いそのものが、楽観バイアスに対するブレーキになります。
予測の振り返りを「方向」で記録する
予測が外れたとき、外れた幅だけでなく、「上に外れたか、下に外れたか」を記録してみてください。
半年分も蓄積すれば、「自分の予測は8割の確率で上に外れている」といったパターンが見えてきます。
この自覚があるだけでも、次の予測は変わります。
予測の「用途」と「責任」をセットで決めておく
「この予測値をもとに何を決めるのか」「外れた場合、誰がどう対応するのか」を予測する前に決めておきます。
用途が明確になると、「とりあえず強気の数字を出しておく」というインセンティブは薄まります。
「なぜズレるのか」を知ることが、予測改善の出発点

需要予測の改善というと、すぐに「もっと高度なモデルを使おう」「AIを導入しよう」という話になりがちです。
しかし、どんなに優れたモデルを使っても、最終的にはその予測値を見て人間が判断を下します。
そして、その判断の過程に楽観バイアスやアンカリング、組織的なインセンティブが介在する限り、モデルの精度だけを上げても同じ問題は残ります。
予測の精度を「当てる技術」ではなく、「ズレの構造を理解する技術」として捉え直すこと。
これが、勘と経験の予測から一歩先に進むための、最も実務的な出発点になるのです。
上振れの原因は、あなたの読みが甘いからではありません。人間の認知と組織の力学が、そう仕向けているのです。
その構造を知ったうえで、どう補正するかを考えること。それが、データを意思決定に活かすということの最初の一歩になります。
今回のまとめ
人間による需要予測は、楽観バイアス・直近の好調期へのアンカリング・「強気に出したほうが社内で安全」という組織インセンティブの3つの力によって、構造的に上振れしやすくなっています。
そしてこの上振れは、過剰在庫や値引き体質の固定化を招くだけでなく、予測プロセス自体の振り返りを阻害し、改善の機会を奪ってしまいます。
解決策は人間の予測をやめることではなく、バイアスの方向を自覚し、ベースラインとの比較や外れ方向の記録といった仕組みで補正していくことです。
「なぜズレるのか」という構造への理解こそが、需要予測を改善するうえで最も大切な出発点になります。

